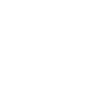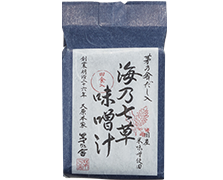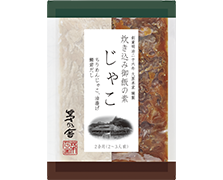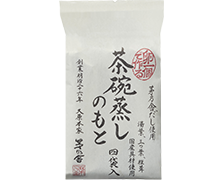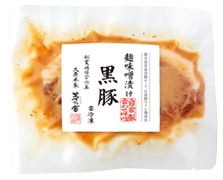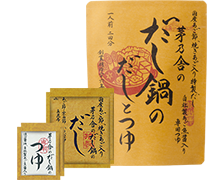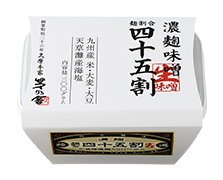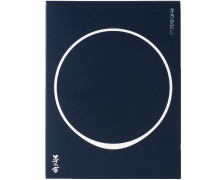冬が来ると何はともあれ、鍋料理。いつもの食材とだしさえあれば、簡単においしくつくれてしまうのが、いちばんの魅力です。そこで今年は、ちょっといい食材を使った鍋料理に挑戦してみませんか。

家鍋をおいしくする技

長ねぎを焼き付けて甘みと香りをだしへ
切りそろえた長ねぎはこんがりと焼き目がつく程度に、あらかじめ焼いておきます。長ねぎから引き出された甘みと香ばしさがだしに移り、より奥深い味わいを楽しめます。

主役のまぐろは大きめの角切り一択
おすすめは2cmの角切り。“まぐろはちょっといい食材”ですから、その持ち味を存分に味わえる切り方を。鍋に入れたら目を離さず、表面の色がさっと変わるくらいでいただきます。

餅にだしを吸わせてだしを味わいつくす
まぐろと長ねぎのうまみが加わった、だしに合わせる〆は揚げ餅。カリッとした餅の表面にだしがじゅわっとしみ込んで、てまひまかけて揚げてよかったと思えるおいしさです。

家鍋をおいしくする技

だしを生かす。茅乃舎だし×骨つき肉で深みを
茅乃舎だしに加え、骨肉からもだしをとることで、だしの味が深くなります。手に入れやすい手羽元や手羽先でも構いません。骨つきの肉を取り入れてみましょう。

焼き目をつけて、香ばしさをアップ
鍋に入れる前に、肉や野菜を焼いて焼き目をつけることで、香ばしさが出て、香りを立たせることができます。ご家庭でできる簡単なひとてまですが、ぐっと違いが出ます。

時間差で具材を煮る
それぞれの具材の役目を生かせるように順番を考えて入れましょう。
- 火をかける前:だしが出る食材
魚・肉・根菜など - だしが温まったら:火を通したい食材
豆腐・茸など - 沸騰後:火を入れすぎると硬くなる食材
薄切り肉・つみれなど - 仕上げ:食感を楽しみたい食材
葉物野菜や薄切り大根・葱など

アクは取りすぎない
アクにはうまみも含まれています。すべてすくわずに、少し残す方がおいしくなります。

だしを味わう鍋は、具を薄切りに
だしを味わう鍋は、具材にだしの含みが良くなるよう、根菜などを薄切りにします。今回も大根はピーラーで薄切りにしています。

卵は2回に分けて、ふわふわに
〆の卵は2回に分けて入れましょう。1回目の卵には火を通し、2回目の卵は、ふわふわと仕上げます。

牛肉で堪能
「白味噌と柚子胡椒の牛鍋」
まろやかな白味噌の風味を、柚子胡椒で爽やかに引き締めた“だし”が、牛肉にほどよく絡んでコクとうまみあふれる鍋に。せりと黄ニラのシャキシャキ食感も軽やかで、箸が進みます。

〆はリゾット風
残った鍋つゆに昆布だし、水(適量)を加えて煮立たせる。ごはん、カレー粉(適量)を加えて煮込み、ミックスチーズを加える。

ぶりで堪能
「薬膳風ぶりしゃぶ鍋」
茅乃舎だしにスパイスや香味野菜を加えた新感覚の鍋。花椒の上品な辛味となつめのほろ苦さが重なる複雑な味わいで、シンプルな具でも最後まで食べ飽きません。具は肉でも美味。

〆は中華麺
残った鍋つゆに椎茸だし、水(適量)を加えて煮立たせる。ごま油、醤油を少々加え、中華麺を加えて軽く煮込む。
今回使用した商品
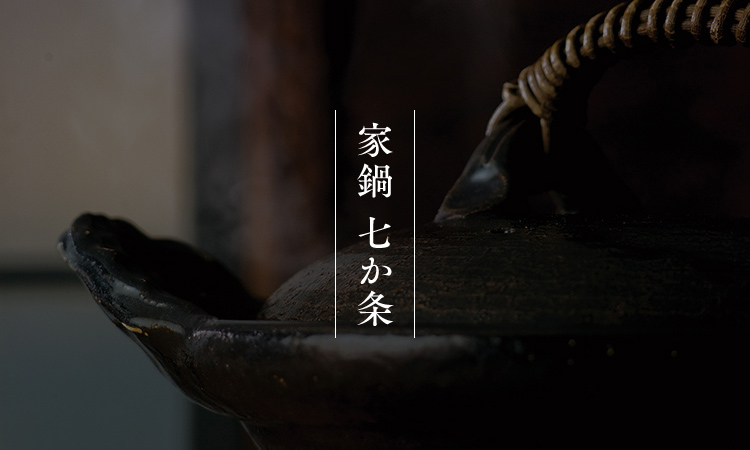
家鍋をどうおいしくするか、楽しむか。知っておくとためになる七つの豆知識をお伝えします。
家鍋 七か条

一、鍋具材の選び方
具は、①うまみが出る食材(肉、茸など)、②水分が出る食材(野菜など)、③味を吸う食材(厚揚げ、油揚げ、麩など)の3パターンで構成されます。この3パターンの具を色彩などを考えながら、バランス良く用意します。

二、茸は、優秀
茸は、一で紹介した①と③を満たす食材で、鍋具材としてとても優秀。昭和の時代からいろんな茸栽培ができるようになりました。茸が身近に一般的になったのも、鍋の進化に影響を与えたと言えるでしょう。ぜひ、いろんな茸を活用しましょう。
三、ごった煮にしない
具材を入れれば入れるほど味が掛け合わされますが、おいしいからと言ってなんでも合わせるとごった煮になります。日本料理では、味を足せば足すほど、雑味を感じると考えられます。ですから、主になる食材は1~2品に絞ること。そうすると、より日本らしい味わいの鍋をつくることができます。

四、鍋の見せ場は、盛り付け
見せ場は、具の盛り付け方と言えます。容量が大きいものから盛っていくのが法則。
例えば、白菜のようなボリューム感があるものを、自分より遠いところから盛り付けます。その手前に茸や豆腐、メインの肉などは一番手前です。こうして盛り付けると、見栄えが良くなります。

五、鍋奉行は、料理上手の役目
鍋奉行とは、鍋の味をコントロールする人です。料理店でも、すき焼き屋では仲居さんが付いて調理するように、味が濃い鍋ほど難しいもの。味の濃さや薄さなど鍋の状況を見ながら具を足していくのが鍋奉行。単に取り分けする役ではなく、料理上手な人が味を調整します。過去には、鍋奉行が座る場所を「かかざ」=お母さんが座る場所とも呼ばれました。

六、もう一品は、酒の肴を
鍋とは、汁物+煮物を合わせた料理です。ですので、もう一品を用意する場合は、煮物や汁物ではなく、酒の肴として挙げられるものがおいしく楽しめます。揚げ物、明太子、塩辛などを選ぶと食卓が華やかになります。

七、鍋の素材を選ぶ
鍋の種類に合わせて、鍋の素材を選ぶと本当のおいしさを味わえます。鍋には、鉄鍋、土鍋、アルミ鍋など素材の違いがあります。すき焼き系など汁が少ないものは鉄鍋やアルミ鍋を使います。寄せ鍋のような煮物系のものは、保温性の高い土鍋を選びます。
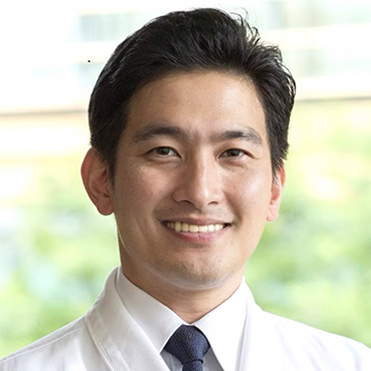
監修:柳原尚之
江戸懐石近茶流宗家。柳原料理教室主宰。博士(醸造学)。東京農業大学 大学院修了。発酵食品学を学ぶ。現在は、東京・赤坂の柳原料理教室で、日本料理、茶懐石の研究指導にあたる。NHK「きょうの料理」などテレビ出演の他、大河ドラマなどの料理監修、時代考証も多く手がける。

ねぎま鍋
程よい脂のまぐろ赤身、冬に旬を迎える長ねぎをほんのりと甘めの醤油だしが引き立てます。食材のうまみを含んだだしも絶品で、余すことなく味わい尽くしたくなります。
材料(2人分)
まぐろ(赤身の刺身)
150g
長ねぎ
2本
生姜
1片
茅乃舎だし【A】
1袋
水【A】
250ml
醤油【B】
大さじ2
酒【B】
大さじ2
みりん【B】
大さじ2
砂糖【B】
小さじ1
作り方
おすすめの〆:揚げた餅に鍋つゆをかけ、おろし大根、お好みで生七味を添えていただく。
- 1. まぐろは2cm角に、長ねぎは2~3cm幅に、生姜は千切りにする。
- 2. フライパンにサラダ油少々(分量外)を熱し、長ねぎを焼き色がつくまで焼く。
- 3. 鍋に【A】を入れ、沸騰後中火で2~3分煮出し、【B】を加える。
- 4. 3に2、生姜を加えて約2分煮て、長ねぎがやわらかくなったらまぐろを加えてさっと火を通す。

鶏すきしゃぶ
茅乃舎だしに加え、骨付きの肉からもだしをとることで味わい深く。大根は薄切りにするとだし含みがよくなります。
材料(2人分)
鶏肉(ぶつ切りや手羽元など骨付き肉)
120g
鶏もも肉(薄切り)
100g
大根
30g
春菊
1/2束
長ねぎ
1本
しめじ
1/2袋
豆腐
1/2丁
茅乃舎だし【A】
2袋
水【A】
600ml
みりん【B】
200ml
砂糖【B】
小さじ4
こい口醤油【B】
100ml
生卵
適量
作り方
〆は、雑炊や麺がおすすめ。生卵を落としておつくりください。
- 1. 大根はピーラーで薄切りにする。鶏もも肉、ねぎ、しめじは、フライパンで焼き目をつける。
- 2. 小鍋に【A】を入れ沸騰後中火で2~3分煮出し、【B】を加える。
- 3. 大鍋で鶏肉(骨つき肉)に焼き目をつけ、2を加え約10分煮る。
- 4. ねぎ、しめじと豆腐を加え、火が通ったら大根、春菊を入れる。
- 5. 鶏もも肉をしゃぶしゃぶする。
- 6. 生卵にくぐらせていただく。

白味噌と柚子胡椒の牛鍋
まろやかな白味噌の風味を、柚子胡椒で爽やかに引き締めた”だし”が、牛肉にほどよく絡んでコクとうまみあふれる鍋に。せりと黄ニラのシャキシャキ食感も軽やかで、箸が進みます。
材料(2人分)
牛薄切り肉
300g
せり
60g
黄ニラ
60g
茅乃舎だし【A】
1袋
水【A】
600ml
白味噌
大さじ4
うす口醤油【B】
小さじ1
柚子胡椒【B】
小さじ1/2~1
作り方
おすすめの〆:残った鍋つゆに昆布だし、水(適量)を加えて煮立たせる。ごはん、カレー粉(適量)を加えて煮込み、ミックスチーズを加える。
- 1. せりと黄ニラは食べやすい大きさに切る。
- 2. 鍋に【A】を入れて強火にかける。沸騰したら白味噌を溶き入れ、弱火にして4~5分煮て、【B】を加える。
- 3. 牛肉、1を加えさっと煮る。

薬膳風ぶりしゃぶ鍋
茅乃舎だしにスパイスや香味野菜を加えた新感覚の鍋。花椒の上品な辛味となつめのほろ苦さが重なる複雑な味わいで、シンプルな具でも最後まで食べ飽きません。具は肉でも美味。
材料(2人分)
ぶり(刺身)
150g
生わかめ
60g
大根
100g
ごま油【A】
小さじ2
花椒【A】
小さじ1
にんにく(薄切り)【A】
1片
生姜(薄切り)【A】
1片
茅乃舎だし【B】
1袋
水【B】
600ml
なつめ【B】
2~3個
酒【C】
大さじ2
うす口醤油【C】
大さじ2
酢【C】
小さじ1/2
作り方
おすすめの〆:残った鍋つゆに椎茸だし、水(適量)を加えて煮立たせる。ごま油、醤油を少々加え、中華麺を加えて軽く煮込む。
- 1. わかめは食べやすい大きさに切り、大根はピーラーで薄切りにする。
- 2. 鍋に【A】を入れて弱火にかける。香りが出たら【B】を加えて強火にし、沸騰後中火で2~3分煮て、【C】で調味する。
- 3. 2に1、ぶりを加えてさっと煮る。